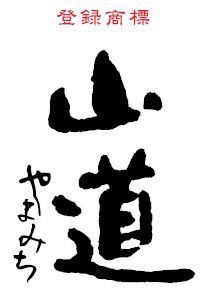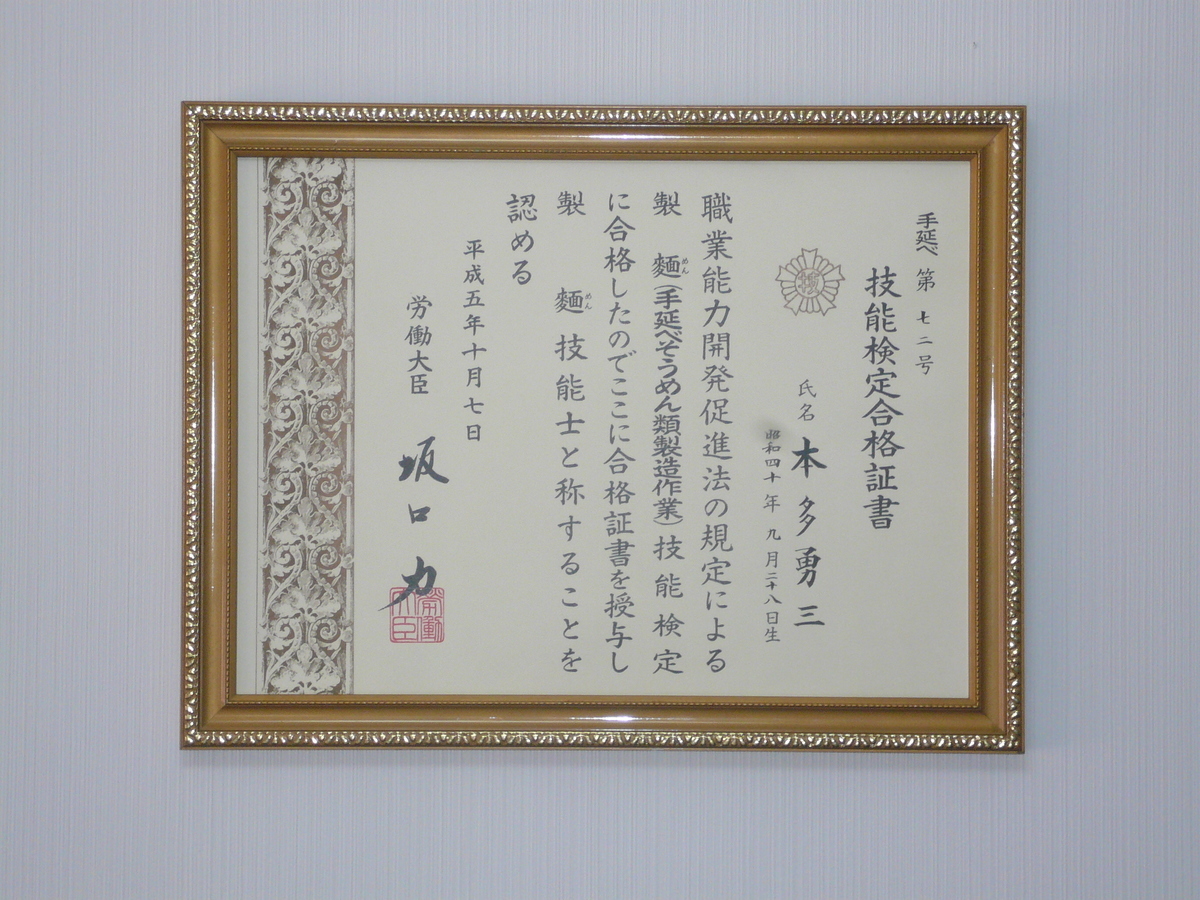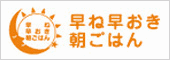島原「そうめんの山道」では、国産小麦100%の手延べ素麺・うどんの製造、無添加だしパックの販売・通販・卸を行なっております。

お気軽にお問い合わせください
0957-85-2866
受付時間 | 9:00~17:00(日祝祭日は除く) |
|---|
手延べそうめんの作り方
毎朝午前3時起き・・・。手延べそうめん作りは夜も明けきらない深夜に始まります。なぜそんなに早起きしなくてはいけないのか? それはそうめんを引き延ばしハタ(そうめんを乾燥する物干し台)に掛け、乾燥する工程を午後1~3時ぐらいに行うためです。一日で一番空気が乾燥する時間帯ですね。手延べそうめんは麺を熟成(寝かせる)させることで引き延ばすことができます。熟成が足りないとプツプツと切れてしまい細くて美しい素麺は出来ません。そのためその熟成時間を考慮すると、どうしても早朝作業になってしまうのです。
そして夕刻、ようやくハタ掛け作業を終え一晩自然乾燥させます。翌朝、本乾燥をして規定の長さに切断するのです。
まる二日がかりの時間を要し、ようやく美味しい手延べそうめんが出来るのです。
縒りかけ熟成法

荒縄
コシ・ハリの強い麺を作るには麺組織を強靭に繋ぎ合わせることが何より重要です。当家では捏ねた麺生地を帯状に切り出し、幾重にも重ね合わせて圧をかけ、麺の基礎となる麺帯を作り上げます。ここから縄を綯うようにらせん状に縒り合せて、また更に縒り合わせ、一筋の麺に仕上げていきます。手間ひまかかる作業の繰り返しですが、ここに美味しさの秘訣が生まれるのです。丸二日間にわたり、あわてず、じっくり、麺の息づかいを聞きながら、真心こめて仕込みます。

棒状に形成した3本の生地を束ねては一本にし、また束ねては一本に・・・何度も縒り合わせて鍛えていきます。

また更に、一本の麺線を縒りをかけながら、徐々に細くしていきます。

熟成中の麺
厚生労働省 技能検定 一級製麺技能士証
お問い合わせはこちら

山道そうめん(金帯、紫帯、黒帯品)は、品質並びに生産工場の衛生状態も含め、島原手延べそうめん認証委員会の厳格な審査基準をクリアした商品です。
ご連絡先はこちら
「近道をせず、山道をゆく。」がごとく一歩ずつ…
そうめんの山道
0957-85-2866
0957-85-2803
infoアットマークshimabara-soumen.com
妻の久美子です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム
住所
〒859-2413
長崎県南島原市南有馬町
丙302番地
代表者
本多 勇三
事業経歴・概要はこちら
アクセスはこちら